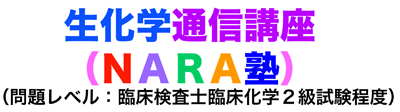
平成20年9月度(第3回)
解答編
![]()
PDF版(180KB) はこちらです
(PDF版は解答のみです。問題編と併せてお使いください)
出題: 藤本一満 会員
| 問題1. | 酵素法によるクレアチニン測定において、試薬成分でない酵素はどれか。 |
| 1. | ペルオキシダーゼ |
| 2. | サルコシンオキシダーゼ |
| 3. | クレアチナーゼ |
| 4. | アデニレートキナーゼ |
| 5. | クレアチニナーゼ |
| . | |
|
【問題1】4 :現在、一般的に用いられているクレアチニン測定試薬は、サルコシンオキシダーゼ/ペルオキシダーゼ法による可視部酵素法である。第一試薬に、クレアチナーゼ、サルコシンオキシダーゼ、ペルオキシダーゼ(第二試薬に含まれている事もある)が添加してあり、第二試薬にクレアニチナーゼが添加してある。 4 のアデレードキナーゼは赤血球中に含まれる酵素であり、クレアチニン測定に関係ない。(なぜ、第二試薬中にクレアニチナーゼが添加してあるのでしょうか?) |
|
| . | |
| 問題2. | ビューレット法による蛋白測定において、試薬成分でないのはどれか。 |
|
1.
|
ヨウ化カリウム |
|
2.
|
ロッシェル塩 |
|
3.
|
EDTA |
|
4.
|
水酸化ナトリウム |
|
5.
|
硫酸銅 |
| . | |
|
【問題2】3 :ヨウ化カリウムは酸化剤でCu2+→Cu1+に還元されることを防ぐ。ロッシェル塩は正式名を酒石酸カリウムナトリウムと言い、水酸化第二銅の沈澱を防ぐ。水酸化ナトリウムは試薬をアルカリ溶液にし蛋白を変性させペプチド結合を露出させる。硫酸銅はペプチド結合4個とキレートさせる2価の銅イオンの供給。それぞれの試薬には役割があります。
|
|
| . | |
| 問題3. | JSCC勧告法によるLD活性測定において、試薬成分はどれか。2つ選べ。 |
|
1.
|
乳酸脱水素酵素 |
|
2.
|
乳酸 |
|
3.
|
酸化型NAD |
|
4.
|
ピルビン酸 |
|
5.
|
還元型NAD |
| . | |
|
【問題3】2 と3 :JSCC勧告法によるLD測定原理は、基質に乳酸、補酵素に酸化型NAD=NADを用い、血清中LDの触媒作用により、乳酸はピルビン酸に、酸化型NADは還元型NAD=NADHに変化する。 |
|
| . | |
| 問題4. | JSCC勧告法による酵素活性測定において可視部測定項目はどれか。 |
|
1.
|
乳酸脱水素酵素 |
|
2.
|
AST |
|
3.
|
ALP |
|
4.
|
CK |
|
5.
|
ALT |
| . | |
|
【問題4】3 :JSCC勧告法で紫外部吸収法:LD(NAD→NADH)、CK(NADP→NADPH)、AST・ALT(NADH→NAD)ALPは405nmでパラニトロフェノール(黄色)の生成速度をみる。 |
|
| . | |
| 問題5. | ウレアーゼ・GLDH法による内因性アンモニア消去ありの尿素窒素測定において、第二試薬成分はどれか。 |
|
1.
|
ウレアーゼ |
|
2.
|
グルタミン酸脱水素酵素 |
|
3.
|
還元型NAD |
|
4.
|
アンモニア |
|
5.
|
α−ケトグルタル酸 |
| . | |
|
【問題5】1 :内因性アンモニア消去法ということから、第一反応:アンモニア+NADPH+α‐ケトグルタル酸 - (GLDH)→ グルタミン酸+NADP で、血清中既存のアンモニアを消去する。第二反応:尿素+H2O -(ウレアーゼ)→ 2NH3+CO2で、1分子の尿素から2分子のアンモニアを生成する。 |
|
| 問題6. | JSCC勧告法によるグルコース測定において、試薬成分でないのはどれか。 |
|
1.
|
アデノシン三リン酸 |
|
2.
|
ヘキソキナーゼ |
|
3.
|
グルコース-6-リン酸 |
|
4.
|
酸化型NAD |
|
5.
|
グルコース-6-リン酸脱水素酵素 |
| . | |
|
【問題6】3 :JSCC勧告法によるグルコース測定法は、 グルコース+ATP - HK → グルコース6-リン酸+ADPグルコース6-リン酸 + NADP - G6PD → 6ホスホグルコン酸 + NADPH である。カッコ内は試薬成分を示す。 |
|
| . | |
| 問題7. | Abell−Kendal法は何の測定法ですか。 |
|
1.
|
尿酸 |
|
2.
|
コレステロール |
|
3.
|
クレアチニン |
|
4.
|
ブドウ糖 |
|
5.
|
C反応性蛋白 |
| . | |
|
【問題7】2 :アベル・ケンダル法はアメリカCDCのコレステロール標準的測定法であり、エステル型コレステロールをアルコール性水酸化カルウムでケン化し、遊離型コレステロールを石油エーテルで抽出し、残さをリーベルマン・ブルハルト反応で発色(無水酢酸/硫酸発色)させる。 |
|
| . | |
| 問題8. | SMBGに関して誤っているのはどれか。 |
| 1. | 測定原理の一つにグルコースオキシダーゼ比色法がある。 |
| 2. | SMBGのMはMonitoringの意味である。 |
| 3. | 血液は1〜3mL必要である。 |
| 4. | 血糖自己測定の事である。 |
| 5. | インスリン治療患者においてSMBGは保険適応である。 |
| . | |
|
【問題8】3 :SMBGとは、Self Monitoring of Blood Glucose の略で血糖自己測定のこと。測定原理には、グルコースオキシダーゼ(GOD)法、グルコースデヒドロゲナーゼ(GDH)法、ヘキソキナーゼ(HX)法、グルコースオキシダーゼ/ペルオキシダーゼ(GOD/POD)法があり前2法は起電流または起電力を測定、後2法は発色させ呈色度を測定。血液必要量は0.6〜2Lが多い。現在、インスリン自己注射を行っている場合のみ保険適応になる。 |
|
| . | |
| 問題9. | アスコルビン酸オキシダーゼ 3KU/Lの試薬50mLを作成する場合、濃厚液3KU/mLの酵素液を何μL採量し、50mLに調製したらよいか。 |
| 1. | 10μL |
| 2. | 20μL |
| 3. | 50μL |
| 4. | 100μL |
| 5. | 200μL |
| . | |
|
【問題9】3 :AODが3KU/L(3000U/L)の試薬50mLということは、 50mL中にはAODが150U存在することになる。濃厚液3KU/mL(3000U/1000μL)のうち50μL(150U)を採量し、試薬50mLに分注すればよい。 |
|
| . | |
| 問題10. |
コレステロールオキシダーゼ/ペルオキシダーゼ法によるコレステロール測定において、モル吸光係数が30000の発色剤を含む第一試薬を用いて、207.4mg/dLのコレステロール標準液を測定した場合、吸光度はいくらになるか。条件:コレステロールの分子量は387。過酸化水素2分子で1分子のキノン色素が生成。試料量15μL、第一試薬量2mL、第二試薬量1mL。反応は100%完了し、発色剤も十分量あるものとする。 |
| 1. | 0.200 |
| 2. | 0.400 |
| 3. | 0.600 |
| 4. | 0.800 |
| 5. | 1.000 |
| . | |
|
【問題10】2 :CHOの分子量387から、207.4mg/dLのモル濃度は5.36mmol/Lとなる。試料15μL、第一試薬2mL、第二試薬1mLから、試料である5.36mmol/Lは0.015/(2+1+0.015)の割合で希釈さ0.027mmol/Lとなる。過酸化水素2分子で1分子のキノン色素生成であるので0.027mmol/Lの半分の0.013mmol/Lが発色することになる。1mol/L=1000mmol/Lで30000の吸光度を持つ発色剤を使用しているので、0.013mmol/Lでの吸光度は0.400 |
|
| . | |
| 問題11. | ペルオキシダーゼの粉末は何色を呈していますか。 |
| 1. | 白色 |
| 2. | 赤褐色 |
| 3. | 青紫色 |
| 4. | 青色 |
| 5. | 緑黄色 |
| . | |
|
【問題11】2 :ペルオキシダーゼは3価の鉄を有しているため、粉末は赤褐色を呈する。
|
|
| 問題12. | MDRD(modification of diet renal disease)の式[(mL/分/1.73m2) = 0.741×175Age-0.203×Scr-1.154を用いて、年齢48才、血清クレアチニン1.0mg/dLの場合のクレアチニンクリアランス値を求めよ。 Age=年齢、Scr=血清クレアチニン。 |
| 1. | 59.1 |
| 2. | 69.1 |
| 3. | 79.1 |
| 4. | 89.1 |
| 5. | 99.1 |
| . | |
|
【問題12】1 :MDRDの式に当てはめて算出すると59.1になる。 |
|
| . | |
| 問題13. | 血液ガス分析装置において実測していない項目はどれか。2つ選べ。 |
| 1. | 重炭酸イオン |
| 2. | 酸素飽和度 |
| 3. | pH |
| 4. | 酸素分圧 |
| 5. | 炭酸ガス分圧 |
| . | |
|
【問題13】1 と2 :血液ガス分析装置はpH、pCO2、pO2の3項目のみ測定。重炭酸濃度、酸素飽和度、BE、酸素含量、炭酸含量等はpCO2、pO2およびHbから計算し求めている。 |
|
| . | |
| 問題14. | 健常人においてヘマトクリット値が45%の場合、ヘモグロビン濃度(g/dL)はおよそいくらか。 |
| 1. | 9.0 |
| 2. | 11.0 |
| 3. | 13.0 |
| 4. | 15.0 |
| 5. | 17.0 |
| . | |
|
【問題14】4 :通常ヘマトクリットの1/3がヘモグロビン量になる。よって、45% /3 = 15g/dL |
|
| . | |
| 問題15. |
正常人血清中のNa:145mEq/L、グルコース:80mg/dL、尿素窒素:15mg/dLの時、血清浸透圧(mOsm/kg�・H2O)はおよそいくらか。 |
| 1. | 260 |
| 2. | 280 |
| 3. | 300 |
| 4. | 320 |
| 5. | 340 |
| . | |
|
【問題15】2 :いくらかの計算式が提唱されていますが、以下の計算式が実測値と一致すると思われます。 |
|
| 問題16. | 溶血の吸収を示す波長でないのはどれか。2つ選べ。 |
| 1. | 340 |
| 2. | 415 |
| 3. | 450 |
| 4. | 540 |
| 5. | 575 |
| . | |
|
【問題16】1 と3 :溶血=ヘモグロビンの吸収帯には、アルファ帯:575nm、ベータ帯:540nm、ソーレ帯:415帯があり、ソーレ帯の吸収はα、アルファ・ベータ帯に比べて大きい。
|
|
| 問題17. | リポ蛋白においてLCAT、CETPおよびHTGLの酵素と最も関係のあるのはどれか。 |
| 1. | CM |
| 2. | VLDL |
| 3. | IDL |
| 4. | LDL |
| 5. | HDL |
| . | |
|
【問題17】5 :LCATはHDL上のアポA?で活性化され、末梢のコレステロールをHDL3中にエステル型コレステロールの形でとりこむ。CETPはHDL2中のエステル型コレステロールを肝臓やLDLに引き渡すときの酵素である。引き渡すと同時にTGを受け取る。受け取ったTGはHTGLにより分解しHDL2→HDL3に戻り、新たに末梢のコレステロールを取り込むことができる。この一連の代謝をコレステロールも逆転送という。 |
|
| . | |
| 問題18. | 食事によって摂取する必要のない脂肪酸はどれか。2つ選べ。 |
| 1. | パルミチン酸 |
| 2. | ステアリン酸 |
| 3. | リノール酸 |
| 4. | リノレイン酸 |
| 5. | アラキドン酸 |
| . | |
|
【問題18】1と2 :食事によって摂取する必要がない=体内で合成できる。ということになり、パルミチン酸やステアリン酸のような飽和脂肪酸は合成可。逆に二重結合が2個以上のリノール酸(C18:2)、リノレイン酸(C18:3)、アラキドン酸(C20:4)は合成できないため食事で摂取する必要があり、必須脂肪酸と言われる。 |
|
| . | |
| 問題19. | 解糖系酵素において高エネルギーリン酸化合物であるホスホエノールピルビン酸と関与する酵素はどれか。 2つ選べ。 |
| 1. | ヘキソキナーゼ |
| 2. | ホスホフルクトキナーゼ |
| 3. | アルドラーゼ |
| 4. | エノラーゼ |
| 5. | ピルビン酸キナーゼ |
| . | |
|
【問題19】4と5 :解糖系で高エネルギーリン酸化合物には2種あり、1,3-ビスホスホグリセリン酸とホスホエノールピルビン酸である。ホスホエノールピルビン酸は順方向ではピルビン酸キナーゼによりピルビン酸に代謝され、逆方向(糖新生)ではエノラーゼにより2ホスホグリセリン酸に代謝される。以上から4 と5 が関与する酵素となる。 |
|
| . | |
| 問題20. | 平均値:200.0mg/dLで変動係数が2.5%のとき、標準偏差(mg/dL)はいくらか。 |
| 1. | ±1.0 |
| 2. | ±2.0 |
| 3. | ±3.0 |
| 4. | ±4.0 |
| 5. | ±5.0 |
|
【問題20】5 :変動係数=標準偏差/平均値×100から、標準偏差=平均値×変動係数/100となる。各数値を当てはめると、標準偏差=200.0×2.5/100=5 となる。 |
|
|
. 【問題11】1級〜2級臨床検査士レベル 【問題12】腎臓学会から発表されたGFRの換算式(eGFR)は必須知識 【問題14,15】知っておくと役立つ知識 |
|
みなさま、いかがでしたでしょうか。おつかれさまでした。
(by 奈良県臨床衛生検査技師会 藤本)